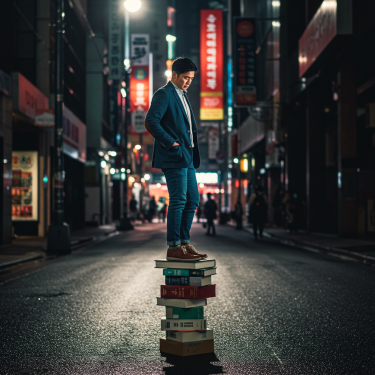はじめに:みんなが経験する「マウント」って何?
「マウント」という言葉、最近よく耳にしますよね。いつの間にか、私たちの毎日の会話にすっかりなじんでいます。SNSを見れば、誰かの「楽しそうな毎日」が目に飛び込んできます。職場の会議では、こっそり自分の手柄をアピールする人がいるかもしれません。友達との何気ないおしゃべりでも、いつの間にか「私のほうが大変」「私のほうが詳しい」といった比べっこになっていることも。そして、家族の集まりでさえ、子どもの成績や夫・妻の仕事の話が、なんとなく優劣をつける空気を作ることがあります。
まるで空気のように、私たちは気づかないうちに「マウント」のやり取りの中にいるのかもしれません。あなたは「あの人、またマウント取ってるな…」と感じたことはありませんか?それとも、「もしかして、私、今マウント取っちゃった?」とドキッとしたことは?なぜ、私たちはときどき人をバカにしたり、自分のほうが上だと見せたがったりするのでしょうか。そして、なぜそんな行動は、私たちをこんなにも嫌な気持ちにさせるのでしょうか。
このブログでは、今の世の中に広がる「マウント」という行動の、もっと深い理由を探っていきます。特に、人が持っている「優越感(自分が上だと思う気持ち)」と「劣等感(自分は下だと思う気持ち)」という二つの気持ちから、なぜ人がマウントを取りたがるのか、その心の仕組みをじっくり見ていきます。この話を通じて、あなた自身の心の中や、周りの人の行動を理解する新しい見方が見つかると嬉しいです。
第1章:「マウント」ってどんなこと?いろいろな形を見てみよう
「マウントを取る」という言葉は、もともと動物の世界で、強い動物が弱い動物の上に乗り、自分の強さを見せる行動から来ています。それが人間の社会でも使われるようになり、精神的に自分が上だと見せる行動を指すようになりました。でも、ただの自慢や自分をアピールすることと、「マウント」は何が違うのでしょうか?
「マウント」のハッキリとした意味は、相手をバカにする気持ちがあったり、気づかないうちに相手の価値を下げて、自分のほうが上だと見せたがったりする行動です。その奥には、他人と比べて自分の価値を確かめ、自分に自信を持ちたいという気持ちが隠れています。自慢は、純粋に自分の喜びをみんなと分かち合いたいという気持ちから来ることもありますが、マウントは相手の反応(うらやましい、自分はダメだ、ねたましいなど)を引き出すことで、自分の優位性を確かなものにしようとする点で違います。
では、具体的にどんな「マウント」があるのでしょうか?いろいろな形を見ていきましょう。
- 地位や実績のマウント: 「私の会社は有名な大企業でね…」「あの仕事は私がリーダーで成功させたんだよ」といった、役職、学歴、お給料、昔の成功体験などを持ち出す場合です。相手の今の状況や努力を軽く見て、自分の社会的地位や実績が上だと見せつけます。
- 知識や情報のマウント: 「そんなことも知らないの?」「それはね、実はこうなんだよ」と、詳しい知識や新しい情報をひけらかし、相手が知らないことを指摘する形です。相手の知識が低いように見せて、自分の頭の良さをアピールします。
- 不幸自慢のマウント: 「私のほうがもっと大変だった」「あなたの悩みなんてたいしたことないよ、私はもっと苦労してるから」と、自分の苦労や不幸を競い合うことで、逆に自分が上だと見せようとするマウントです。相手の悩みを小さく見せて、自分の忍耐力や経験の多さを自慢します。
- 謙遜(けんそん)マウント: 「いやいや、私なんてまだまだ…(でも本当はすごいんです)」と、一見控えめなふりをしながら、遠回しに自分をアピールするずるいマウントです。「たまたま運が良かっただけで、〇〇大学に合格しちゃって」「たいしたことない料理だけど、みんなに美味しいって言われちゃって」といった形で、相手に「そんなことないですよ!すごいですね!」と言わせることを期待します。
- 子育てや家庭のマウント: 「うちの子はもう〇〇ができるのよ」「夫(妻)が〇〇で、本当に助かってるわ」と、子どもの成績、習い事、夫・妻の仕事、家庭のお金持ちぶりなどを持ち出す場合です。特にママ友の間などでよく見られ、自分の家庭が幸せで優秀だとアピールします。
- 経験マウント: 「それなら私も経験済みだけど、もっとすごいのは…」と、自分の経験の多さや質で相手を上回ろうとするアピールです。相手の体験を「たいしたことない」と見なし、自分の経験がいかに特別であるかを強調します。
- 見た目やファッションのマウント: 「その服、流行遅れじゃない?」「私、最近ダイエット成功して、〇〇キロ痩せたの」など、見た目やセンス、流行に敏感かどうかで優劣をつけようとするものです。特に女性の間でよく見られ、相手の見た目やファッションをけなすことで、自分の優位性を確立しようとします。
これらのマウント行動は、された人にとても嫌な気持ちやプレッシャーを与えます。バカにされたと感じたり、自分の価値が低いように思えたり、プライドが傷ついたりするからです。マウントは、人間関係を壊し、コミュニケーションを邪魔する大きな原因になりかねません。
第2章:優越感を求める気持ち:なぜ人は「上」に立ちたがるの?
人はなぜ、こんなにも「上」に立ちたがるのでしょうか?その根本には、人が生まれつき持っている気持ちと、今の社会の仕組みが深く関わっています。
認められたい気持ち(承認欲求)と関係が深い
人間の心について研究したアブラハム・マズローという人は、人の願いを5つの段階に分けました。その中で、「認められたい気持ち(承認欲求)」は、自分に自信を持ちたい、自分を大切にしたいという気持ちとして、人とのつながりを求める気持ちよりも上の段階にあります。「認められたい」「評価されたい」「尊敬されたい」「特別な存在だと思われたい」という気持ちは、誰もが持っているものです。
マウント行動は、この「認められたい気持ち」を満たすための一つの方法になることがあります。他人より自分が上だと感じることで、一時的に「自分は価値のある人間だ」「自分はすごい」という感覚を得られるからです。例えば、自分の成功した話をすることで、相手から褒められたり、うらやましがられたりする視線を引き出し、それによって自分の存在価値を確かめようとします。これは、まるで乾いた地面が水を求めるように、認められたい心がマウントという形で現れているのかもしれません。
自分に自信がないこと(自己肯定感が低いこと)と関係が深い
しかし、この「認められたい気持ち」の裏には、しばしば自分に自信がないこと(自己肯定感が不安定だったり低いこと)が隠れています。心から自分を肯定できない人は、外からの評価や他人と比べることでしか、自分の価値を測れない傾向があります。
本来、自己肯定感とは、ありのままの自分を受け入れ、肯定する気持ちのことです。でも、それが十分に育っていない場合、人は他人をバカにしたり、自分のほうが上だと見せつけたりすることで、一時的に自分の価値を高め、心の隙間を埋めようとします。これは、まるで壊れやすいガラス細工を補強するために、外側から丈夫なカバーをかぶせるような、自分を守るための行動だと言えるでしょう。他人をけなすことで、相対的に自分を高く見せようとするのは、自分自身の価値に自信が持てないからなのです。
社会での競争とプレッシャー
今の社会は、よく「競争社会」と言われます。「勝ち組」「負け組」といった言葉が象徴するように、私たちはいつも他人と比べられ、競争を強いられる環境で生きています。学歴、仕事、収入、結婚、子育て、そしてSNSの「いいね」の数まで、あらゆる面で優劣がつけられがちです。
このような環境では、「負けたくない」「置いていかれたくない」「人より優れていたい」という気持ちが、気づかないうちに私たちの行動を支配することがあります。この社会的なプレッシャーが、マウント行動を増やす大きな原因となるのです。他人より少しでも前に出たい、少しでも上だと見せたいという焦りが、気づかないうちにマウントという形で現れてしまうのです。
自分を守るための優越感
さらに、優越感は、自分の弱さ、不安、そして隠れた劣等感を覆い隠すための「仮面」として働くこともあります。人は、自分の弱点やコンプレックスに直面すると、心に痛みを感じます。その痛みから逃れるために、気づかないうちに「自分は完璧だ」「自分は間違っていない」と思い込もうとすることがあります。
これは、フロイトという心理学者が考えた「防衛機制」の一つとも言えます。自分の中にある不安や劣等感を認めず、それを打ち消すかのように、必要以上に自分が上だと主張することで、心の落ち着きを保とうとする、自分をだますような心の動きです。マウント行動は、この自分を守るための行動の一部として現れることも少なくありません。

第3章:劣等感の裏返し:マウントの隠れた理由
優越感を求める気持ちの裏側には、しばしば「劣等感(自分は下だと思う気持ち)」が隠れています。驚くことに、マウントを取る人の多くが、実は心の中に強い劣等感を抱えている可能性が高いのです。マウントは、その劣等感を隠したり、乗り越えようとしたりする行動だという見方から、その深い理由を探っていきましょう。
劣等感とマウント行動は深くつながっている
心理学者のアルフレッド・アドラーは、人の行動の多くは、劣等感を乗り越えようとしたり、自分が上だという気持ちを求めたりすることから生まれると考えました。マウント行動もまた、この劣等感の裏返しだと考えることができます。
自分の劣等感を刺激されるような状況に出くわすと、人は心に嫌な気持ちを感じます。その嫌な気持ちから逃れるため、あるいは劣等感を打ち消すために、攻撃的な態度や、やりすぎなマウント行動に出てしまう心の仕組みが働くのです。例えば、学歴にコンプレックスを持っている人が、高学歴の人に対して知識でマウントを取る、といったケースがこれに当たります。自分の弱点を刺激されたくない、あるいは弱点があることを知られたくないという気持ちが、マウントという形で現れるのです。
劣等感の種類とマウントへの影響
劣等感にはいろいろな種類があり、それぞれが異なるマウント行動に影響を与えます。
- 体の劣等感: 見た目、体つき、運動能力など、生まれつきの体の特徴やコンプレックスを抱えている場合、人はそれを補うかのように、他の分野で自分が上だと主張しようとすることがあります。例えば、運動が苦手な人が、頭の良さやお金持ちぶりでマウントを取る、といった形です。
- 心の劣等感: 人とのコミュニケーション能力、頭の良さ、相手の気持ちを理解する力、ユーモアのセンスなど、内面的な能力に関する劣等感を抱えている場合、知識マウントや、相手を言い負かすマウント、あるいは皮肉や批判といった形で現れることがあります。相手の意見を否定したり、自分の知識をひけらかしたりすることで、自分の頭の良さが上だと保とうとします。
- 社会的な劣等感: お金持ちかどうか、社会での立場、育った家庭環境、出身地などに関する劣等感は、ブランド品自慢、役職のマウント、あるいは昔の成功を自慢することにつながることがあります。今の自分の状況に不満や不安がある場合、それを隠すために、昔の成功や持っているものを自慢することで、自分が上だと見せようとします。
劣等感を乗り越えられない心の状態と悪い循環
劣等感と真剣に向き合い、それを受け入れることは、とても難しいことです。多くの人は、自分の弱点やコンプレックスから目を背けたいと考えます。マウント行動は、一時的にその劣等感から目を背け、自分が上だと感じることを可能にします。しかし、それは根本的な解決にはなりません。
むしろ、マウント行動を繰り返すことで、人間関係は悪くなり、周りから孤立してしまいます。すると、さらに認められたい気持ちが満たされなくなり、劣等感が深まるという悪い循環に陥ってしまうのです。マウントは、劣等感という心の病を一時的に楽にする「麻薬」のようなものであり、根本的な治療にはならないのです。
「投影」とマウント
心理学の考え方に「投影」というものがあります。これは、自分の心の中にある、受け入れたくない気持ちや特徴(劣等感、不安、怒りなど)を、気づかないうちに他人に「押し付ける」心の動きです。
マウント行動の中には、この「投影」が関係しているケースも少なくありません。例えば、自分が「ダメな人間だ」という劣等感を抱えている人が、他人のちょっとしたミスを必要以上に厳しく批判したり、相手の能力をけなしたりすることで、一時的に自分の劣等感から目を背け、自分が上だと見せようとします。相手を攻撃することで、自分の中の嫌な気持ちを外に出し、心のバランスを保とうとするのです。
このように、マウント行動は、ただ傲慢なだけでなく、複雑な劣等感や不安が絡み合って生まれる、とても人間らしい行動だと言えるでしょう。
第4章:マウントを「する人」「される人」それぞれの気持ちとどうすればいいか
マウントという行動は、する側とされる側の両方の心に影響を与えます。それぞれの気持ちを理解し、適切に対応することで、いらないストレスを減らし、もっと良い人間関係を築くことができます。
マウントをする人の気持ちと背景をもう一度確認
まず、マウントをする人の気持ちをもう一度確認しましょう。彼らの行動は、決して単純な悪い気持ちだけから来ているわけではありません。
- 認められたい気持ちが満たされない: 彼らはいつも他人から評価されたり、褒められたりすることを求めていて、それが得られないと強い不安を感じます。マウントは、その認められたい気持ちを得るための方法なのです。
- 自分に自信がない(自己肯定感が弱い): 心から自分を肯定できないため、表面的な優位性や他人と比べることでしか自分を認められません。自分自身を信じる力が弱いからこそ、外からの評価に頼ってしまうのです。
- 人との関係を作るのが苦手: マウントという形でしか他人との関係を作れない、あるいは人との良い関わり方を知らない場合もあります。相手をコントロールしたり、自分が上だと見せたりすることでしか、人間関係の中で自分の居場所を確保できないと感じているのかもしれません。
- 気づかないうちにしてしまう行動: 一番困るのは、本人がマウントをしていることに気づいていない場合です。昔の経験からくる習慣や、周りの環境がマウントを増やしている場合、悪い気持ちなく、あるいは「良かれと思って」マウントをしてしまうこともあります。彼らは、自分の言動が相手にどんな影響を与えているかをわかっていないのです。
マウントをされる人の気持ちと具体的な対処法
マウントをされた側は、とても嫌な気持ちや怒り、劣等感を感じることがほとんどです。なぜなら、マウントは、された人のプライドを傷つけ、価値を否定されたように感じさせるためです。自分の存在が脅かされるような感覚になることもあります。しかし、その感情にとらわれすぎると、心に大きな負担がかかってしまいます。
ここでは、マウントをされたときにどうすればいいか、いくつか具体的な方法をご紹介します。
- 物理的・精神的に距離を取る: これが一番効果的な方法です。もし可能なら、マウントをする人との接触をできるだけ減らしましょう。職場でそれが難しい場合は、心の中で「この人はこういう人だ」と割り切り、心の中で距離を保つことが大切です。相手の言葉を真剣に受け止めず、「右から左へ受け流す」ようなイメージを持つと良いでしょう。
- 聞き流す・受け流す: 相手の言葉を真剣に受け止めず、感情的に反応しないことが大切です。あいづちを打つ程度にして、「ふーん」「そうなんですね」「なるほど」と軽く流すことで、相手のマウントしたい気持ちを満たさないようにします。相手は反応がないと、だんだんつまらなくなり、マウント行動をエスカレートさせにくくなります。
- 共感する(でも注意が必要): 相手の劣等感や不安に寄り添う姿勢を見せることで、相手が安心し、マウント行動が収まる場合もあります。例えば、相手が自慢話をしているときに、「それは大変でしたね」「頑張りましたね」と、その努力や苦労に焦点を当てて共感を示すことで、相手の認められたい気持ちを良い形で満たしてあげられるかもしれません。ただし、相手の自慢話に必要以上に同調したり、褒めすぎたりしないように注意が必要です。
- 質問で返す: 相手のマウント発言に対して、具体的な質問を返すことで、相手に自分の発言を客観的に見させ、マウント行動をしていることに気づかせるきっかけを与えることができます。「具体的にどういうことですか?」「それはどうしてそう思うんですか?」など、事実を確認したり、もっと詳しく聞いたりするような質問は、相手が勢いで話していたマウントを冷静に見つめ直すきっかけになります。
- はっきり自分の気持ちを伝える: 許せないマウント行動に対しては、冷静かつはっきりと「そういう言い方はやめてください」「その話は私には関係ありません」と伝えることも大切です。感情的にならず、きっぱりとした態度で自分の境界線を引くことで、相手にこれ以上踏み込ませないという気持ちを示すことができます。ただし、相手との関係や状況をよく考えてから行動する必要があります。
- 自分の価値観をもう一度確認する: 一番大切なのは、相手の評価や言動に惑わされず、自分自身の価値観、得意なこと、目標をもう一度確認することです。他人と比べるのではなく、自分自身の成長に目を向けることで、マウントの影響を受けにくくなります。「私は私」という揺るぎない自分への自信を持つことが、心を強くします。
- ユーモアで返す: 状況によっては、軽いジョークやユーモアでマウントをかわすことも効果的です。例えば、自慢話に対して「それはすごいですね!私には逆立ちしても無理です!」と笑いながら返すなど。ただし、相手との関係や場の空気を読むことが大切であり、相手を怒らせてしまう可能性もあるため、慎重に使いましょう。
第5章:マウント社会をうまく生きるヒント:自分に自信を持つ力を育てる
マウント行動が、たとえ一時的に自分が上だと感じる気持ちをもたらしたとしても、結局は人間関係の溝を深くし、孤立を招き、最終的には自分自身の幸せを損なうものであることを、もう一度確認しました。では、私たちはこの「マウント社会」をどう乗り越え、もっと豊かで良い人間関係を築いていけば良いのでしょうか?そのカギは、「健全な自己肯定感(自分に自信を持つ力)」を育てることにあります。
マウントの連鎖を止める
まず、私たち一人ひとりが意識すべきは、「マウントの連鎖を止める」ことです。自分がマウントをしないことを意識し、また、マウントをされてもその嫌な気持ちに流されないことで、悪い連鎖を止める第一歩となります。誰かがマウントをしてきたときに、それに感情的に反応して言い返したり、自分もマウントで対抗したりすることは、さらにマウントの争いを増やすだけです。
「自分軸」を持つことの大切さ
他人と比べることに縛られず、自分自身の心の中にある基準(大切なこと、信じていること、目標)で自分を評価する「自分軸」を持つことがとても大切です。
- 心の中の基準で自分を評価する: 学歴、収入、役職、持ち物といった外側のことで自分の価値を測るのではなく、自分が何を大切にしているか、何に喜びを感じるか、どう成長したいかといった、心の中の基準に目を向けましょう。
- 努力と過程を評価する: 成功や失敗といった結果だけでなく、そこに至るまでの努力や過程、そしてそこから学んだことを評価する視点を持つことが大切です。結果がどうであれ、自分が一生懸命取り組んだこと、成長できたことを認めましょう。
いろいろな価値観を認め、尊重する
人はそれぞれ違う背景、経験、能力を持っています。その違いを優劣の基準にするのではなく、個性として認め、尊重する気持ちを持つことが、マウントのない社会を作る上で欠かせません。
- 「完璧」を目指すのではなく、「ありのままの自分」を受け入れる: 誰もが完璧ではありません。自分の不完全さや弱点も個性の一部として受け入れ、肯定することで、他人からの評価に必要以上に左右されなくなります。
- 他人との違いを尊重する: 自分と違う意見や生き方を持つ人に対しても、興味を持ち、敬意を持って接することで、新しい発見や学びが生まれます。いろいろな価値観を認め合うことで、マウントをする必要がなくなっていきます。
健全な「認められたい気持ち」の満たし方
「認められたい気持ち」は人間にとって自然なものです。でも、それをマウントという良くない形で満たすのではなく、もっと良い方法で満たすことを意識しましょう。
- 身近な人との良い人間関係: 家族や親友など、信頼できる人との間で、ありのままの自分を受け入れてもらう経験を増やすことが、自分に自信を持つ力を高めます。お互いに支え合い、認め合う関係の中で、本当の意味で認められることができます。
- 自分の成長を感じられる活動: 趣味、ボランティア、仕事など、自分が夢中になれる活動に打ち込むことで、心の中からわき上がる達成感や、自分にはできるという気持ちを得られます。これは、他人からの評価に頼らない、揺るぎない自分への自信の源となります。
- 感謝の気持ちを伝えたり、受け取ったりする: 日々の生活の中で、他人に感謝の気持ちを伝えたり、逆に感謝される経験を増やすことで、良い気持ちの循環が生まれます。これは、人間関係の質を高め、自分に自信を持つ力を育てる上でとても効果的です。
人との良い関係を作る
マウント社会から抜け出すためには、競争するのではなく、助け合い、相手の気持ちを理解しようとするコミュニケーションを心がけることが大切です。
- 相手の良いところを認め、尊敬する: 他人の良い点や得意なことを見つけ、それを素直に認め、尊敬する気持ちを持つことで、健全な人間関係を築くことができます。相手をライバル視するのではなく、一緒になって学び、成長できる仲間として考えましょう。
- オープンな話し合い: 自分の意見を正直に伝えつつも、相手の意見にも耳を傾け、理解しようと努力するオープンな話し合いを心がけましょう。話し合いを通じてお互いの理解を深めることが、マウントが入り込む隙をなくします。
まとめ:マウントの先に広がる、もっと豊かな人間関係
このブログを通じて、私たちは「マウント」という行動が、たとえ一時的に自分が上だと感じる気持ちをもたらしたとしても、結局は人間関係の溝を深くし、孤立を招き、最終的には自分自身の幸せを損なうものであることを、もう一度確認しました。その根本には、誰もが持っている「優越感(自分が上だと思う気持ち)」と「劣等感(自分は下だと思う気持ち)」という、人間らしい気持ちが複雑に絡み合っているのです。
優越感や劣等感は、人間である限り誰もが持っている自然な気持ちです。大切なのは、これらの気持ちとどう向き合い、どうコントロールするか、そしてどう良い形で表現していくかです。マウント行動は、これらの気持ちが良くない形で現れたものにすぎません。
このブログが、あなたがマウントの心の仕組みを深く理解し、それによって生まれる嫌な気持ちや悩みが少しでも楽になる助けになれば嬉しいです。そして、他人と比べることに縛られず、自分自身の価値を心の中から見つけることで、もっと自分に自信を持つ力を育て、最終的にはマウントとは無縁の、本当に豊かな人間関係を築くための一歩を踏み出すきっかけとなることを心から願っています。
さあ、あなたにとっての「本当の豊かさ」とは何でしょうか?そして、その豊かさを手に入れるために、今日から何を変えていけるでしょうか?